2025年6月12日(土)~22日(日)、なら歴史芸術文化村(以下、文化村)では アトリエ併設型国際展覧会「ボーダークロッシングス展―行き来する、その先へ―子どもと自然とデジタル」を開催し、約1000名の方々にご来場いただだきました。
(主催:JIREA【Japan Institute for Reggio Emilia Alliance】
一般社団法人ORIECC【Organization for Research on
International Education and Care for Children】
共催:みりおらーれ、なら歴史芸術文化村)

本展は「子どもと自然とデジタルの出会い」をテーマに、イタリア
レッジョ・エミリア市の乳児保育園、幼児学校の教育実践事例をパネルや映像資料で紹介し、その事例と繋がるアトリエを体験する展覧会です。
これまでに世界7カ国19の都市で巡回展が開催されてきました。日本では今回が初公開で、2025年1月東京都会場を皮切りに、石川県、長野県を巡回し、最後に奈良県で開催されました。
レッジョ・エミリア市では近い将来、子どもたちがコンピューターを使用する時代がくると予測し、1980年代からデジタルを取り入れた教育が行われてきました。
自然との出会いの中でデジタルを活用することにより、「自然とデジタル」という一見異なるように思えるこの2つは、どのように交錯し、そこからどんな出会いや対話が生まれてきたのでしょうか。


この展覧会の魅力のひとつは、開催地ならではの自然や文化を活かした展示が行われることです。文化村は、施設全体が「道の駅」として登録された多機能複合施設です。歴史、芸術、食と農などに触れることができる4つの棟(文化財修復・展示棟、芸術文化体験棟、交流にぎわい棟、情報発信棟)から構成され、文化・地域振興を行う拠点となっています。
私たちはこの特色を活かし、奈良県にゆかりのある以下の素材を提供しました。


・一枚一枚職人の手で漉かれ、文化財修復にも使用される「吉野手漉き和紙」
・文化財修復・展示棟からいただいた「鉋くず」
・200年以上前にお寺で使用されていた「瓦」
・奈良の地場産業である「蚊帳生地」
・交流にぎわい棟の文化村にぎわい市場や地域の方々からいただいた「植物」
会場となった芸術文化体験棟3階は、新緑の山々が見渡せるテラスと自然光が心地よく差し込むフロアです。展示されたこれらの素材は、天候により日々表情が変化していく姿が印象的でした。
本展のタイトル「ボーダークロッシングス展―行き来する、その先へ―子どもと自然とデジタル」の通り、会場内には多様な世界が混じりあう出会いの場となっていました。イタリアの教育実践事例と奈良の素材が交わり「世界と地域」の交流が生まれる場。そして、教育実践事例が来場者の学びにつながり、新たな対話を生み出す場。
こうした中で、来場者はそれぞれ自らの感覚で“ボーダークロッシングス”を体感することとなりました。
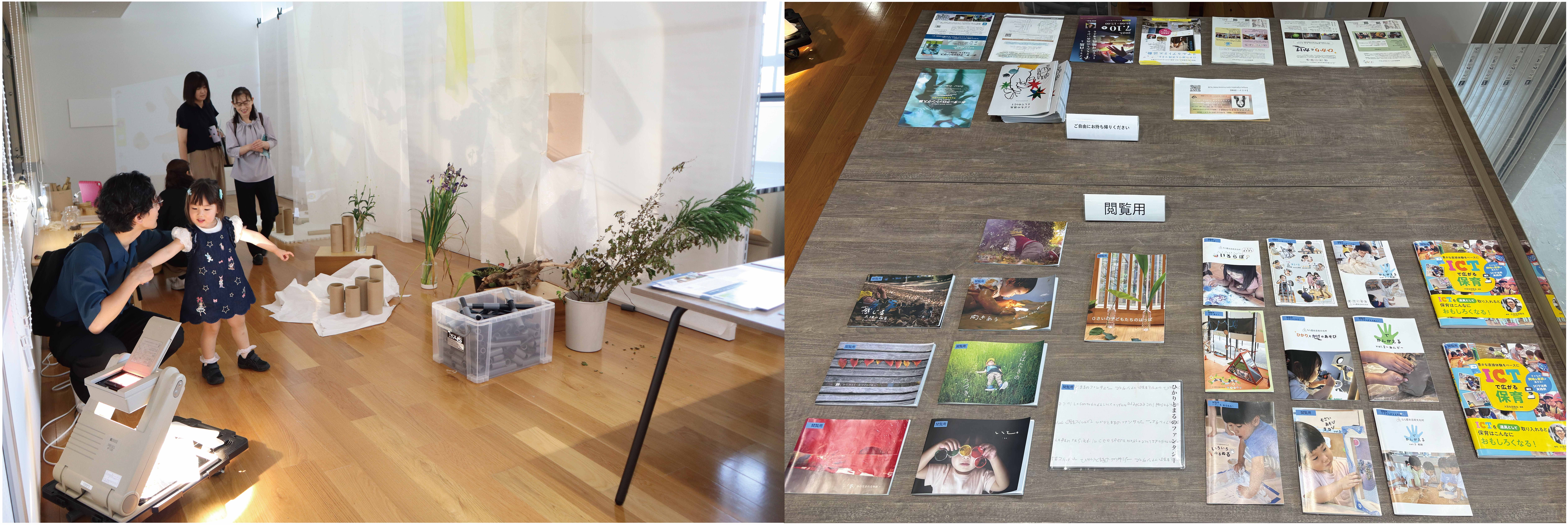
また、来場者が実際に体験を通して、素材や道具とじっくり関わってほしいという思いから会場内には、文化村独自のエリアとして「体験スペース」を設けました。スペース内には、マイクロスコープやオーバーヘッドプロジェクター(OHP)などを使用して体験できるコーナーやドキュメンテーション・書籍の閲覧コーナーもあり、年齢問わずたくさんの方々に手に取っていただきました。
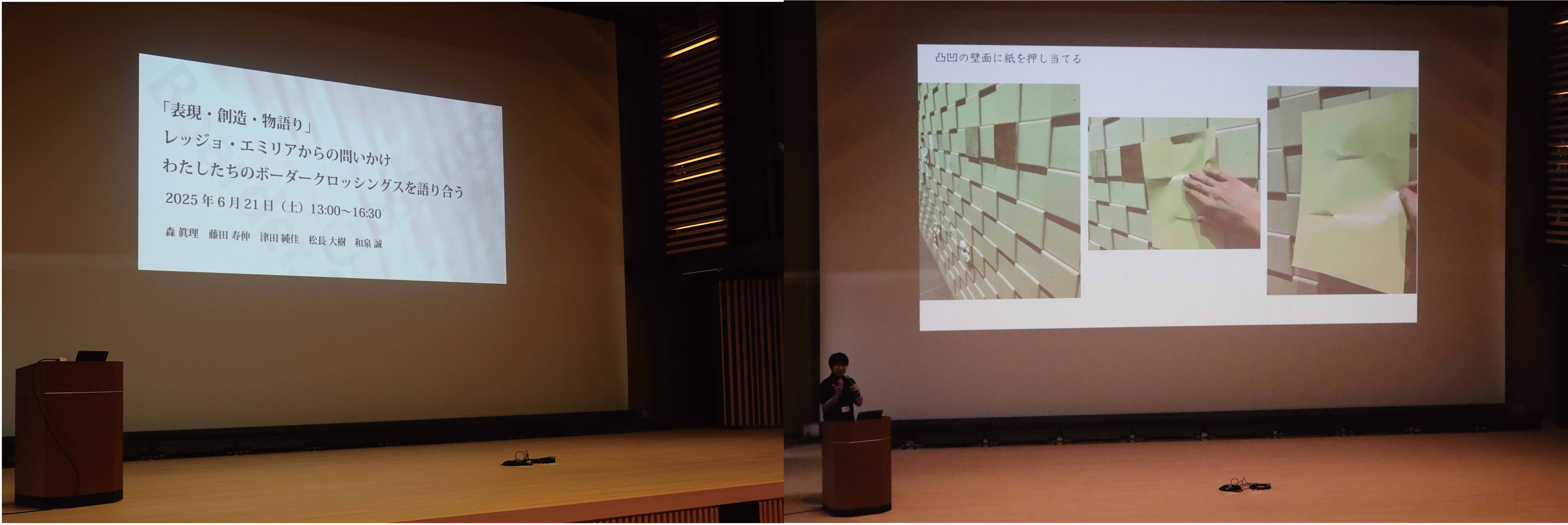
6月21日(土)にはシンポジウム「表現・創造・物語り
~レッジョ・エミリアからの問いかけ わたしたちのボーダークロッシングスを語り合う~」が開催されました。
文化村からは幼児向けアートプログラムの実践を紹介し、多くの方に取り組みを知っていただく機会となりました。
今回のテーマである「自然とデジタル」の体験では、デジタルツールを情報獲得のための手段としてだけでなく、探索するツールとして活用することで、肉眼では見ることができない世界を発見し、心が動く瞬間がありました。
この心が動く瞬間を子どもたちはきっと、日々たくさんの境界線を行き来して体験していることでしょう。
その瞬間を次に繋げるためには、子どもの気づきに共感し探究心を持った大人の関わりが大切です。また、さまざまな人や環境と出会うことで学びがより広がっていくことと思います。
過去の教育実践事例がいまの私たちの学びにつながり、未来を生きる子どもたちにつながっていくー。展覧会を通して、映像やドキュメンテーションで記録を残していくことの意味や対話を重ねていくことの大切さを改めて実感しました。
文化村の幼児向けアートプログラムにおいても、子どもと関わる中で「大人はどう関わる存在であるべきか」を問い続けながら、私たち自身も学びを深めていきたいと思います。